真田家とは、かつては敵対関係にあった。
幸隆殿が仕えるようになってから、真田の武力も謀略も抜きん出た戦に父上は感心し、真田家を重用した。
そして主従の証の人質にと、送られたのが昌幸だ。
幼名は源五郎であった。
左右白黒の色の違う髪型が目を引いて、他の者は奇異の目で見ていたが私は違った。
躑躅ヶ崎館に来たばかりの源五郎は、知らぬ大人達に囲まれて幸隆殿の袖に隠れていた。
とても小さく可愛かった。
今思えば、あれが一目惚れであったのだろうと思う。
「どうかなさいましたか」
「昌幸は、まこと、可愛いよな」
「…嬉しく、ないのですが…」
「父上も、幸隆殿も信綱も昌輝もそう言っていたぞ?」
「あの方々は…、全く…」
眉を寄せて笑う。やはり昌幸は愛おしい。
元服して昌幸の名を与えられた。
私達は幼き頃からの友だが、今では友という言葉だけでは収まりきれない関係である。
私は昌幸を愛している。
「勝頼様、勝頼様…」
「昌幸」
切なげな声色で私を呼ぶ昌幸に応えて口付ける。
その声に呼ばれて雪崩るように昌幸を押し倒した。
恋しい愛おしいという想いを感じたまま、思ったままに昌幸に伝えたら困らせてしまうと思い、数年はその想いを秘めていた。
最早偽れぬと恐る恐る本心を伝えてみれば、昌幸は破顔して私を受け入れてくれた。
昌幸も同じ想いを抱いていたと、告白してくれたのだ。
それから私達は恋仲の関係になった。
幸隆殿は隠居され、真田家当主は今や兄の信綱だ。
頭も口も回るが、信濃衆であり奥近習上がりの昌幸の身分はそれ程高くはない。
身分など瑣末なことであり、私の友であるという扱いを変えるつもりはない。
私の中では友という言葉では収まりきらない。
昌幸は平静を装いながら、表面上は偽り、裏では堪えているような性格だ。
彼奴の大丈夫は、本当は大丈夫じゃない事の方が多い。
こと、昌幸の兄ら信綱や昌輝はその事を知っていて、昌幸をよく見ている。
私もそれを知ったが故に、昌幸をほおっておけない。
我慢に慣れ過ぎた昌幸をよく見て、何かと庇っていた。
肌を合わせている時でさえ、気付いてやらねば昌幸は無理をするものだから気が気ではない。
だめ、やめて、などの言葉は照れ隠しであるが、嫌だという拒絶の言葉は本当に辛い時だ。
過ぎた快楽は苦痛になり、それは乱暴になってしまう。
誰よりも大切な昌幸を、私の独りよがりで傷付けたくはない。
「勝頼様…」
「昌幸」
「ん…、ぅ…」
肌着のみを身につけた昌幸を押し倒し、繋がっている箇所に触れる。
触れれば熱く、接合部の隙間に指を含ませればひくひくと指を締め付ける。
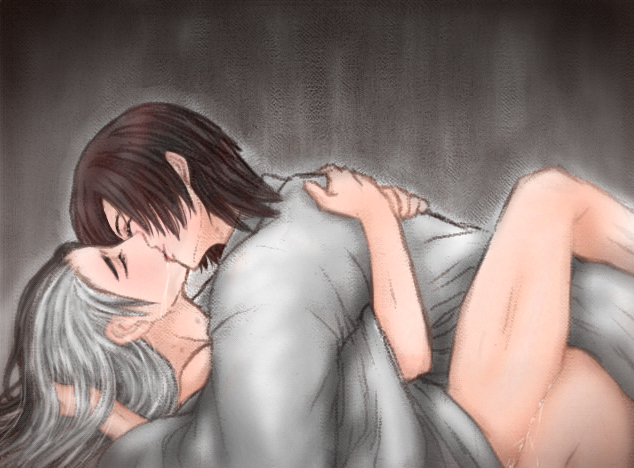
幾度目かの接合で、昌幸はとろとろに蕩けている。
互いに吐き出した精液が白濁として、私達の太股や腹を濡らしていた。
昌幸の髪を撫で、後頭部を支えながら昌幸に深く口付け、奥に腰を突き上げた。
遠慮がちに背中に回される手に微笑み、腰に絡まる脚に目を細めた。
「…かつよ、り、さま…、も、う」
「そんなに締めるな…嬉しくなる」
「っ、ぅ…、ん…っ!かつ、よりさま…」
「は…、昌幸…」
程なくして昌幸が果て、その締め付けに促されて私も昌幸の中に果てた。
今の昌幸は私の事しか考えられない。
智将謀将であるとされる真田昌幸が今は私の事しか考えられないのだ。何と幸せな事だろうか。
いつも昌幸を想っているが、今は特段に昌幸の事しか考えていない。
ずっとこうしていられたらいいのにと呟くと、距離があるからこそ、限りある時だからこそ愛おしいと昌幸は零した。
無論、本当は共に暮らしたい。
遠くに居てもいつも互いを想い、触れ合えば手と手を携えて過ごしてきた。
機を見て娶ると昌幸に言うのだが、何を馬鹿なとはぐらかされてしまう。
私は本気であるのだが、立場や身分や性別が昌幸を即答はさせなかった。
胸を上下させ呼吸を乱している昌幸に寄り添い、頬を撫でた。
果てたばかりの昌幸の身は過敏過ぎる。
悪戯に攻め続ける事も出来ようが、善がり狂わせるのはまた今度の機会としよう。
今宵は昌幸を虐めたい訳ではないのだ。
動かない事に気付いたのか、昌幸は安堵した様子で私を見上げていた。
とろんと蕩けた瞳は私だけを見つめている。
「落ち着いたか」
「…、はい…」
「おいで、昌幸」
「勝頼様…」
汗ばんだ肌着を脱がせて、私の膝に座るように促した。
私の肌着は昌幸が脱がせてくれた。
横向きに座らせて、どちらともなく唇を合わせる。
舌を絡ませ腰に手を回すと、昌幸が肩に手を回してくれた。
昌幸の体躯は良いが、私よりは細い。
腰をぐっと引き寄せると、ぴんと立った乳首が目に入った。
触れる度に体の感度が良くなっているように思う。
先程とて、昌幸は随分と善がり私より幾度も先に果てていた。
「…随分、感度が良いな」
「あなたが、触れるからです…」
「昌幸」
「っ、は、端ないと…思われまするか」
「…可愛いな、昌幸は」
「何ですか…、もう、っひ…ゃっ」
胸に触れ、そのまま乳首に触れる。
まだ情事を止めたつもりはない。首筋を吸い痕を遺しながら指で抓る。
口元を抑えて声を堪える様子に、下から昌幸の胸に吸い付く。
「っ、かつより、さまっ…」
「此処でも、感じるようになったか」
「あ、あなたが、そう、お躾に…」
「全く…。艶っぽくなり過ぎだぞ。私は気が気ではない」
「あ、あの…」
胸を揉み、指で解せば柔らかい乳首と胸である。
昌幸は男らしい引き締まった腹筋ではあるのだが、胸は柔らかい。
私がいつも揉んでるからかなと首筋を噛んでいると、口元に手をやり眉を下げた昌幸が不安げに私を見ていた。
「何か言いたげだな、昌幸」
「…飽きもせず触れられますが、私に乳房はないのですよ」
「昌幸の胸は柔いぞ?」
「あなたとそう変わらないのでは」
「触ってみるか?」
困り顔で振り向く昌幸に向かい合わせに座るよう促す。
やはり昌幸の顔が見れた方が良いなと一度口付けて、手を取り私の胸に触れさせた。
私も鍛錬は怠っていない為、胸筋はそれなりにある。
昌幸が触れたところと同じところに触れると、やはり昌幸の胸は柔らかい。
「固い…」
「鍛えているからな!」
「私はどうして」
「昌幸は、私が育てているから仕方ない」
「っ」
「私の指を埋めるようになっただろう?昔はこうじゃなかった」
「か、勝頼様っ」
昌幸の乳首は、指で押せば柔らかく食い込む。
幾度かそれを繰り返し片方は吸い付いていると、昌幸は赤面して唇を噛んでいた。
傷になると口の中に指を入れると、口内が蕩けていた。
口内の柔らかさは体にも比例する。また熱を燻らせているのだろう。
首筋に手を添えて口付けて、昌幸を見上げる。
小さく息を吐きながら、瞳を揺らして私を見つめてくれていた。
私のも再び勃ち上がり、昌幸の中に入りたいと腹に擦る。
「っ…かつより、さま…」
「そのまま腰を落とせるか、昌幸」
「は…、い…」
「辛くなったら、ちゃんと言うんだぞ?」
「だいじょうぶ、です…、っ…ん…!」
昌幸に当てがい、腰を撫でつつ下に下にと腰を落とさせる。
中から私の子種が溢れるほど、昌幸とは情事を重ねているが何度抱いても足りない。
首に回してくれた腕を見て微笑み、昌幸を見上げて笑う。
昌幸も釣られて笑ってくれた。
少し辛そうに眉を寄せるものだから、これを最後にしてやらねば明日に響いてしまうだろう。
昌幸に負担をかけぬよう私から腰を押し付けて抽迭を繰り返した。
今度は緩く柔く。昌幸がぞくぞくと体を震わせて私を感じてくれているのが分かる。
きゅうと締め付ける昌幸に微笑み、再び胸を吸うと締め付けがきつくなった。
胸だけでも相当感じるようになったらしい。
私が育てた甲斐があったものだ。
「っ、そんな、そこ、ばかり…」
「ふふ、こんなに締め付けてくれてるぞ?」
「い、言わないで…ください…っ」
少し体を拗らせて奥に穿つ。
昌幸も限界だろう。
横抱きにするようにして体勢を変えると、眉を下げつつも昌幸は笑ってくれた。
私にしか見せぬ笑みだと自負している。
「昌幸、昌幸」
「はい…、勝頼様…」
「愛しているぞ」
「…はい…、はい、私も…、勝頼様」
舌を絡めてそのまま深く口付ける。
昌幸の唇は柔らかくて、つい食みたくなってしまう。
腰を引き寄せて首筋を噛むと締め付けがいっそうきつくなった。
もう果てたいのだろう。頬を撫でて昌幸のに触れつつ、悪戯心に胸にも触れた。
ぴんと立っている乳首を甘く噛みつつ、昌幸を果てに促しながら私も最奥に腰を進めた。
「っ…、ひ、ぅ…!」
「は…、っ、昌幸、まさゆき」
「かつ、よりさま…っ」
同時に果てるべく抽迭を早める。
今一度口付け、奥に突き上げ昌幸の中に果てる。
幾度目かの射精に昌幸の中はぐちゅぐちゅと音が立っていた。
昌幸も果てて、私の肩に凭れ吐息を吐いている。
瞳が潤み、睫毛が濡れて綺麗だ。
白と黒の髪を撫でつつ、額に口付けて肩を撫でた。
敷布を敷いて、昌幸を寝かせた。
私の上着を肩に掛け、すぐ傍に私も横になる。
疲労を滲ませつつも、私が駆け寄れば身を寄せて掌に甘えてくれる。
「昌幸は可愛いな…」
「…ん…」
「源五郎の頃から変わらないな、昌幸」
「四郎様の方が愛らしゅうございました…」
事後の気怠い雰囲気を好いている。
私の腕を差し出すと、ふわりと笑って頭を乗せてくれた。
そのまま背中にまで手を回して抱き締めると、本当に嬉しそうに笑ってくれる。
私の前でだけ昌幸は素直になってくれた。
「まさゆき」
「はい」
「昌幸、愛しているぞ」
「はい…」
何度そう伝えたか知れないが、昌幸はいつだって頷いて私の想いを受け止めてくれた。
いつだって頬を染めて微笑んでくれる。
何時だったか、自分の何処が好きなのか昌幸に聞かれた事がある。
暫し思い悩み俯いていたら、昌幸は不安がり瞳を伏せていた。
「ふふ…」
「どうされました…」
「昌幸が、私の何処が好きなのですか?と聞いた事があったな」
「はい」
「あの時の昌幸は可愛かったな」
「…応えがないものですから、もしやないのではないかと…」
「そんな訳ないだろう?それに昌幸の全部好きだと言ったではないか」
「はい…。全部と仰いました」
「今でも変わらないぞ。昌幸の全部、ぜーんぶ好きだからな」
「…勝頼様の事も、全て…私はお慕いしております…」
「っ、昌幸」
「おやすみなさい…、勝頼様」
「お、おう、おやすみ昌幸」
今の言葉は初めて聞いた。
眉を下げて微笑む昌幸だったが、疲労が堪えたのか瞼を閉じてしまった。
間もなく聞こえてきた寝息に微笑む。
昌幸は華奢ではないが、細身の腰を抱き寄せると腕の中に収まる。
今だけは私に甘えているのだろう。
手に馴染む白と黒の髪を撫でながら、額に唇を寄せる。
今は緊張も矜持も何もない。
私の前でだけ、昌幸がただの昌幸で居てくれる事が嬉しかった。
昌幸を抱き寄せて私も瞼を閉じた。
湯殿で昌幸が自分の胸に触れて俯いていた。
どうしたのだと傍に駆け寄ると、昌幸の胸がぷっくりと腫れてしまっていた。
どうやら私が弄りすぎたらしい。
「…勝頼様…」
「す、すまぬ、昌幸。そのままでは痛いだろう。さらしを巻いてやろう」
「どうしてくれるのです…」
「では、責任を取って娶るとしよう」
「っ、勝頼様」
「私は本気なんだぞ、昌幸」
昌幸の背を胸に抱きながら、湯船で二人きり、早朝の湯を楽しんでいた。
胸を腕で隠しつつ、昌幸は私の真っ直ぐな瞳を直視できないのか、視線を逸らしてしまった。
「こぉら、逃げるな昌幸」
「私は男です」
「そうだな」
「わ、私は信濃の、真田の…」
「知ってるぞ」
「勝頼様とは、身分が」
「今更、何が問題なんだ!」
「も、問題しかありませぬ!」
「むう、昌幸がうんと頷いてくれるまで言い続けるからな!」
「っ…、勝頼様」
「だって、愛してるんだぞ。こんなに好きなんだ。ごっこ遊びをしているつもりはないのだからな。私は昌幸と一緒に生きていたいんだ」
「…逆上せてしまいます…」
「それは大変だ。もう上がろうか」
顔を真っ赤にして昌幸は項垂れていた。
昌幸の頬につうと涙が伝ったように思えて心配して顔を覗き込むと、昌幸から口付けてくれた。
私は昌幸の不意打ちに弱い。
昌幸よりも顔を赤くしていると、昌幸がゆるりと微笑む。
ああ、この顔だ。この瞳が好きなんだ。
「…愛しています…」
「おう、ちゃあんと知っているとも」
「それはそれは…」
「私も逆上せてしまった」
「もう上がりましょう」
「うー、昌幸。ずっと好きだからな昌幸」
「はい。ちゃあんと知っております」
私の言葉を使って昌幸が微笑む。
本当に、幸せそうに。
その顔が見れただけで、私も幸福を感じた。
手を取り腰を取り、昌幸を気遣い布巾に包む。
濡れた白と黒の髪が艶やかに光っていた。
昌幸と二人、布巾に包まり額を合わせる。
私より少し小さな昌幸が、不意に源五郎であった頃の事を思い出させる。
初見の一目惚れであったあの頃から、昌幸の魅力は衰えるどころか増すばかりだ。
あの頃から今でもずっと想いは変わらない。
昌幸を胸に抱き寄せて微笑むと、昌幸も私を見上げて笑ってくれた。